
ソフトウェア業界のM&Aは、技術革新と市場ニーズの変化により急速に進行しています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の成長戦略として重要視される中、ソフトウェアソリューションを提供する企業の価値が一層高まっています。
また、AIやクラウドサービスの導入が進むことで、企業間の提携や統合が必要となり、M&Aが一つの有効な手段として選ばれることが増えています。この記事では、ソフトウェア業界のM&Aの動向や事例・売却相場について解説します。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

データの集計や企業の実務処理を目的として、システムの企画や設計、それに関わる開発を行い、またシステム運用に際して実務や保守を(その一部を担う場合も含めて)請け負う事業を行っているのがソフトウェア業界です。企画から運用や保守まで一貫して行う場合、特にシステムインテグレーター(SIer)と呼ぶこともあります。
ソフトウェア企業は、経産省の調査で5つに分類されています。依頼を受けて独自のソフトウェアを開発し、その運用保守までを行う受託開発ソフトウェア業(いわゆるSIer)、家電や通信機器などの特定の機能に資するソフトウェアを開発する組み込みソフトウェア業があります。
またPC用のマニュアルセットで販売されるプログラムやプリインストールのプログラムを開発するパッケージソフトウェア業、そのうち特にゲーム機などのゲームソフトを開発するゲームソフトウェア業もあります。5つ目はホームページ作成やSEO(検索エンジン最適化)にあたる受託ホームページ・SEO業です。
自社で開発したソフトをクラウド上で提供している、いわゆるSaaSにあたる企業はソフトウェア業ではなく、計算サービスや調査サービスなどを行う情報処理・提供サービス業に分類されています。
ソフトウェア市場の規模は、2009年に15兆636億円に達しました。しかしリーマンショックによる世界的な不況の影響で、翌2010年には2兆円近く縮小してしまいます。その後の金融緩和などの対策によりソフトウェア投資も徐々に回復し、2013年以降13~14兆円の堅調な市場規模を保っていました。しかし、2025年現在では、デジタルトランスフォーメーションの加速やAI技術の普及により、市場規模はさらに拡大し、15兆円を超える規模に成長していると推測されます。
昨今の動向としては、受託開発システムを導入するケースよりもクラウドサービス導入の比重が大きくなってきたことや、AIやIoTの浸透に合わせパッケージソフトウェア業や組み込みソフトウェア業の活況が予想されていることが見受けられます。ソフトウェア業の比重が上がるに連れ、人材不足は慢性的になってきています。自社のITスキルを向上させるための内製化も手伝って、ソフトウェア業、ユーザー企業の双方で人材の不足が懸念されています。
またクラウドでの業務の拡大に合わせて、必ずしもソフトウェア企業がユーザー企業と近くにある必要はなくなり、地方発の事業の可能性が広がってきています。顧客としてのユーザー企業の要求は多岐にわたっており、そのビジネスの拡大と相まってソフトウェア企業とのグループ化によるシナジー効果を期待する傾向も強まっています。
特に、デジタルトランスフォーメーションの進展により、企業は競争力を維持するために最新の技術を採用しなければならず、それがM&Aの促進要因となっています。多くの企業は、技術とリソースを持つ他の企業との合併や買収を検討することで、自社の技術基盤を強化し、市場での優位性を確保しようとしています。
また、AIや機械学習を活用したソリューションニーズも高まっており、これを満たすためにソフトウェア企業は他業種との連携を模索するようになっています。結果として、異業種間でのパートナーシップや提携が進み、新たなビジネスモデルの構築が期待されています。
典型的なビジネスモデルは、ユーザー企業(顧客)の発注を元請けとなるSIerが受けて進める形です。顧客の要望を受けながらシステム開発について企画し、要件を確認しながら個々の業務内容に振り分けます。システムの基本設計を定め、部分設計や個々のプログラム開発については、下請けの協力会社に指示して開発を進めます。
最終的には元請けのSIerが統括してプログラム間の連携や全体の稼働をテストし納品、その後保守、運用にあたります。
近年では、クラウドサービスの普及に伴い、従来の受託開発モデルからSaaS(Software as a Service)型ビジネスモデルへのシフトが進んでいます。これにより、顧客は初期投資を抑えつつ、必要なソフトウェアを利用できるようになり、企業側も継続的な収益を確保しやすくなります。
SIerは、大きく3つの系統に分かれます。
1つ目はPCなどのハードウェアを生産するメーカー系の企業です。日立製作所、富士通、NECなどのトップ企業が並びます。
2つ目は顧客企業の情報システム部門の子会社企業です。野村総合研究所、伊藤忠テクノソリューションズなどが挙げられます。
第3に独自の資本系統による独立系の企業です。大塚商会、TISなどがその例です。

ソフトウェア業界のM&Aは、同種企業や関連企業と業務強化の目的で進められるものや、異業種間でシナジー効果を期待して進められるものなど、多様な形があります。ここでは5つの事例を、そのスキームや目的などを含めて紹介します。
株式会社デジタルガレージ(DG)は、2023年7月1日に株式会社フィーリスト(フィーリスト)の株式を取得し、同日付で「株式会社DGフィーリスト」へ社名変更することを発表しました。フィーリストは北海道札幌市を拠点とし、全国に6拠点を有するシステム開発会社で、約120名のエンジニアを抱えています。この買収は、DGの総合決済プラットフォームを中心とした「DG FinTech Shift」に基づき、収益のリカーリング化や非連続事業の創出を推進するための重要な一手と位置づけられています。
購入背景には、テック人財の増強があり、フィーリストの優れたエンジニア育成環境と技術力を活かすことで、DGグループの競争力の強化を目指しています。フィーリストは2015年に創業し、主にWebシステムやスマートフォンアプリの開発を手掛けており、技術者の育成に力を入れることから、高い定着率を誇っています。また、フィーリストの本拠地となる札幌市は「GX金融・資産運用特区」としてスタートアップの育成に注力しており、この地域での事業展開は本社の渋谷区との相乗効果を生むと期待されています。
デジタルガレージ執行役員の佐々木智也氏は、DGフィーリストの技術力によってDGグループのエンジニアリソースを増強し、新たな価値創造への取り組みを加速すると述べています。また、DGフィーリストの代表取締役社長である吉野俊文氏も、グループインに際してエンジニア技術力の向上を目指すとともに、新たな仲間を求める姿勢を示しています。
この買収は、経済的な背景や地域特性を考慮した戦略的な動きであり、今後の成長を視野に入れたものであると言えます。デジタルガレージは持続可能な社会の実現を目指し、今後も新たな挑戦を続ける方針を示しています。
2024年4月8日、アクセンチュア株式会社は株式会社クライムを買収する合意を発表しました。この買収により、クライムの提供するITソリューションがアクセンチュアのサービスに統合されることになります。クライムは1989年に設立され、主に金融や製造業、通信事業者、行政機関に向けたシステム開発やITインフラに関するサービスを提供してきました。特に、勘定系や基幹系のシステム開発において高い評価を受けています。
クライムは約230名の社員を擁し、特に約200名のエンジニアが高度な専門知識を持っている点が特徴です。彼らはクラウド、セキュリティ技術、アプリケーションマネジメントサービス(AMS)に精通しており、これらのスキルはグローバルな場面でも重要視されています。アクセンチュアはクライムの技術力を取り入れ、特にデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進める上で大きな力量を加えられることになります。
クライムとの統合後、アクセンチュアは顧客に対してより深いデータ駆動型経営の支援を行うことができるようになります。また、クライムのエンジニアが国際的なプロジェクトに参加することで、スキルアップの機会が提供され、地域や日本全体の経済成長にも寄与します。なお、買収の具体的な条件については公表されていませんが、アクセンチュアはこの買収を通じて、より強固な市場ポジションを築くことを目指しています。
ウエルシアホールディングスは2024年1月17日に、株式会社エクスチェンジおよびその完全子会社であるエクスチェンジソリューションズ、エクスチェンジクリエイティブの買収を発表し、3月15日付で実際の株式譲渡が完了しました。エクスチェンジからは200株が譲渡され、取得割合は100%です。このことにより、エクスチェンジグループはウエルシアグループの一員として新たに運営を開始します。
エクスチェンジグループは、2003年に設立されて以来、情報システムの設計・開発・運用や、ソフトウェアの受託開発を主な事業として成長してきました。特にWeb系のサーバーシステムやアプリケーション開発においては、確かな技術力と豊富なノウハウを基盤として運営しており、これまでに数多くの実績を積み重ねています。連結で140人規模の専門家を有するエクスチェンジグループは、企画から設計、開発、運用に至るまでの一連の工程を自社内で完結できる強みを持っています。
ウエルシアグループは、この買収を通じてITインフラやアプリケーションなどの情報システムの整備を進め、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に必要なIT企画・開発・運用体制の構築を加速させる方針です。これにより、生活者に新しい価値を提供しつつ、企業自身の持続可能な成長を実現するウエルシアモデルの進化を目指しています。
ウエルシアは、買収によって獲得した技術やリソースを活用し、より高度な情報システムを構築することで、競争力の強化を図る意向を示しています。今後の事業戦略として、エクスチェンジグループの専門性を生かし、ウエルシアの業績向上に寄与することが期待されています。
株式会社データ・アプリケーション(DAL)は、2023年10月に株式会社WEELを完全子会社化したことを発表しました。この買収により、WEELはDALのグループ企業となり、両社は新たなシナジーを生み出し、サービス向上と事業発展を目指します。
WEELは、生成AIを活用したシステムの受託開発やコンサルティング、AIメディアの運営を行っている企業です。この買収を通じて、DALはデータ連携に関する自社のソフトウェアとWEELの技術を融合させることで、顧客への提案力をさらに強化します。特に、AIとデータ連携の領域でのソリューション提供により、企業の情報システムの効率化を図ることが期待されています。
今後の展望として、DALとWEELは合同でウェビナーを実施し、両社の取り組みをクライアントに紹介する予定です。また、データ連携ビジネスの加速にも注力することで、企業に対するデータ連携基盤の提案を行い、DALの製品導入も併せて提案します。この取り組みは、データを効果的に連携させるための基盤として重要な役割を果たします。
さらに、DALは自社の製品群にAIの機能を取り入れ、その市場価値を向上させる計画を立てています。具体的には、エンタープライズデータ連携プラットフォーム「ACMS Apex」やデータハンドリングプラットフォーム「RACCOON」の強化などが挙げられます。これにより、自動化機能や予測機能をさらに高め、システムの安定稼働を支援します。
アクモスは、2023年12月21日に、株式会社プライムシステムデザインの株式を取得し、連結子会社化することを決議しました。プライムシステムデザインは、1998年に設立され、業務システムやソフトウェアの受託開発及びシステムエンジニアリングサービス(SES)を提供してきました。特に、製造業向けの業務システム開発や、IoT関連事業に力を入れており、幅広い業界のお客様に対して高い技術力と豊富な経験を活かしたソリューションを提供しています。
今回の株式取得により、当社はプライムシステムデザインと協力し、首都圏地区におけるシステムエンジニアリングサービスの事業拡張を進める計画です。両社のシナジーを生かすことで、ITソリューション事業のさらなる成長を遂げられると期待しています。具体的には、プライムシステムデザインの受託開発能力を活用し、顧客のニーズに応じた柔軟で高品質なソフトウェア開発が可能になります。これにより、当社グループ全体の競争力が強化され、市場での優位性を確立することが見込まれます。
半導体素材の大手JSRは、2023年10月17日、官民ファンドである産業革新投資機構(JIC)による株式公開買い付け(TOB)が成立したと公式に発表しました。TOB成立に際して、JSRの議決権の約84%が応募され、JICは約9000億円を投じてJSRの全株式取得を目指しています。このうち、残る株式についても手続きを進め、遅くとも2023年夏には完全子会社化し、上場廃止となる見通しです。
JSRは、半導体製造に使用されるフォトレジストの世界的なリーダーであり、この革新によって国際競争力を一層強化する計画を立てています。JICキャピタルのCEO池内省五氏は、JTの核となる役割を果たし、半導体材料業界の再編を図る意向を示しています。今後は短期的な業績に依存することなく、中長期的視点での戦略投資を重視し、業界全体の構造改革を推進する方針です。
このTOBは、政府が経済安全保障のために半導体産業の強化に取り組んでいる中で行われており、JSRが「国策会社」となることで、業界の再編とともに日本の競争力強化が期待されています。具体的には、JSRが他の日本のメーカーと連携し、さらなる技術開発や製品革新を進めることが考えられています。
アステラス製薬株式会社は、2023年7月11日、米国のバイオ医薬品企業Iveric Bio社の買収を完了したことを発表しました。この買収は、同社の間接子会社であるBerry Merger Sub, Inc.を通じて実施され、事前に7月6日に行われたIveric Bio社の臨時株主総会で承認を受けた後、独占禁止法の関連承認を含む条件が満たされることで正式に完了しました。
この買収により、Iveric Bio社はアステラス製薬の子会社として新たなスタートを切ることとなり、同社の株式はNASDAQ市場から上場廃止となりました。
2024年2月6日、KDDI、三菱商事、ローソンの3社は資本業務提携契約を締結し、共同経営体制への移行を発表しました。この提携は、「リアル×デジタル×グリーン」というコンセプトのもと、新たな生活者価値の創出を目的としています。具体的には、KDDIと三菱商事がローソンの株式をそれぞれ50%保有し、今後の経営を共同で行っていく方針です。
KDDIは、ローソンに対して公開買付け(TOB)を実施する予定です。本取引の完了後、三菱商事とKDDIは、ローソンの議決権を50%ずつ保有する見込みです。
共同経営体制の移行により、KDDIとローソンは、リアル・デジタル融合型サービスの開発に加え、ポイント経済圏の拡大などに取り組んでいく予定です。例えば、KDDIが有する約3100万人の顧客データと、ローソンの約1万4600店舗での1日あたり約1000万人の来店者データを統合し、より多様なサービスを提供することが期待されています。
株式会社SYSホールディングス(3988)は、2023年10月に茨城県土浦市に本社を置くつくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の全株式を取得し、子会社化することを発表しました。この買収により、つくばソフトウェアエンジニアリングはSYSホールディングスのグループ企業となります。実際、つくばソフトウェアエンジニアリングは、映像編集ソフトウェアを主力製品としており、ソフトウェアの受託開発にも注力している会社です。
さらに注目すべきは、つくばソフトウェアエンジニアリングの子会社であるTHAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD(タイ バンコク)が、同社の98%の株式を保有している点です。SYSホールディングスが株式を取得することで、THAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTDはSYSホールディングスの孫会社となります。これにより、SYSホールディングスはタイ市場へのアクセスを得ることができ、現地の日系企業との取引機会を拡大することが期待されています。
株式会社テンダは、2022年5月18日に、ソフトウェア受託開発企業である三友テクノロジー株式会社の全株式を取得し、子会社化することを決定しました。このM&Aの目的は、テンダ自身のエンジニアリング機能を強化し、専門的な領域での顧客基盤の獲得を図ることです。
テンダはクラウドサービスの提供、スマートフォン向けソーシャルゲームやアプリの開発、さらにWebシステムやモバイルサイトの構築を手掛けており、近年のデジタルトランスフォーメーションの流れを背景に急成長を遂げています。一方の三友テクノロジーも業務アプリやスマートフォンアプリの開発、コンサルティングサービスを提供しており、双方のシナジー効果が期待されます。
このM&Aにより、テンダはエンジニアリング工数単価の増加を図るとともに、間接生産性を向上させ、全体的な効率化を目指します。また、テンダが持つクラウドサービスと三友テクノロジーの受託開発技術を組み合わせることで、より多様なサービスを顧客に提供できるようになります。
2020年12月、ソフテックの全株式を取得したサイバーセキュリティクラウドが同社を子会社化しました。
このM&Aにより、クラウド型のWebセキュリティサービスを行うサイバーセキュリティクラウド社は、ソフテックの脆弱性管理ソフトウェアやセキュリティ診断サービスのノウハウを共有し、ビッグデータ活用や販売チャンネルの拡大などをねらいました。
同種企業のM&Aによる企業力の強化を図った例です。
近年、サイバーセキュリティの重要性が増す中で、企業間の競争も激化しています。
このため、事業の強化を目指す企業が、専門的なノウハウを持つ企業と連携する動きが増えてきました。
特に、IT業界では信頼性の高いセキュリティサービスを提供することが競争優位につながるため、M&Aは戦略的な選択肢として注目されています。
今回のような事例は、同業者間でのシナジー効果を生むだけでなく、より広範な市場のニーズに応えるための重要なステップといえるでしょう。
2021年7月、すでにBlue Yonderの株式の20%を持っていたパナソニックが、残る80%の譲渡を受け、同社を完全子会社化しました。
パナソニックはDXによる現場プロセスのイノベーション事業を行っていましたが、ソフトウェア事業を強固なものとするためその専門企業であるBlue Yonderの買収を図ったものです。
大手のSIerが、事業の強化、拡大を図る目的で行われたM&Aの事例です。このM&Aは、パナソニックにとってAIと機械学習を活用したサプライチェーン管理の強化を意味します。
Blue Yonderは、その革新的なソフトウェアソリューションを通じて、顧客の運営効率を向上させることが評価されており、パナソニックの監視対象となっていました。
M&Aを通じて、パナソニックは競争力を強化し、デジタルトランスフォーメーションの加速を図ることが期待されています。このように、業界内での戦略的な合併は、企業が市場のニーズに柔軟に応える一つの手段として重要な位置を占めています。
2020年12月、マクアケがジシバリの全株式を取得して、子会社化を経て吸収合併しました。
マクアケは、クラウドファンディングを運営する企業で、Webサービスを行っています。このWebサービスにおけるシステム開発力の向上、管理コスト削減に関係する業務の効率化を図る目的で、Web上でのサービスやアプリ開発で実績のあるジシバリを自社のものとすることにしたわけです。
自社のソフトウェア部門の内製化、効率化を図る目的で行われたM&Aです。
このM&Aにより、マクアケはジシバリの持つ技術力と専門知識を活かし、迅速なサービス展開が可能になると期待されます。
特に、ジシバリが持つ開発ノウハウは、マクアケのクラウドファンディングプラットフォームの機能向上に寄与し、クライアントへのサービス提供の質を一層高めることが見込まれています。
マクアケの戦略的なM&Aは、競争が激化する市場において、より強固な地盤を築くための重要なステップとなるでしょう。
2020年12月、トヨタ自動車からの出資をミックウェアが受ける資本提携が決定されました。
ミックウェアはカーナビシステムや自動運転の支援プログラムなどを開発している企業です。トヨタ自動車は、未来のモビリティ社会の実現に向け、自社製品に実装するソフトウェアや新規の技術開発を発展させることをねらっています。
大手企業がソフトウェア企業の持つポテンシャルを獲得しようとしたM&Aの事例です。
この資本提携により、トヨタ自動車は先進的な技術の獲得とともに、競争力を一層強化することが期待されています。自動運転技術やスマートシティの実現に向けた取り組みが加速する中で、ミックウェアとの連携は新たなビジネスチャンスを創出する可能性があります。
両社の協力により、未来のモビリティ社会の実現に向けた技術革新が進むことが期待されるでしょう。
2022年2月、出光興産はスマートスキャンとの資本業務提携に合意しました。出光興産は石油関連事業を展開するエネルギー企業ですが、同社のサービスステーションを利用した予防医療サービスの展開を目論み、すでにスマートスキャンと共同で脳ドックサービスを提供する車両の実証に取り組んでいました。
スマートスキャンは健康に関するデータプラットフォーム開発など医療系のソフトウェア企業です。出光興産がデジタルエコシステムを開発し、自社のサービスステーションに新たな価値創出を目指すためのM&Aとなります。
この提携により、出光興産は新しいビジネスモデルを構築し、顧客に幅広い健康管理サービスを提供できるようになります。
スマートスキャンの先進的な技術を活用することで、予防医療を推進し、顧客ニーズに応える施策が期待されています。
このような企業のコラボレーションは、業界全体の変革を促進し、技術革新を通じた新たなソリューションの創出に寄与することが期待されています。

ソフトウェア業界は技術開発が日進月歩で進められ、市場規模も拡大方向となっています。そしてM&Aによる業界再編が進んでいます。
M&Aの増加傾向の要因の一つは、投資分野としての可能性の高まりです。金融緩和により投資市場が活況を呈している中で、クラウドの活用、ビッグデータの可能性、IoTの普及などの成長要素の多いソフトウェア業界はよい投資対象です。実際リーマンショックで前年比10%近い落ち込みを見せた大企業のソフトウェア投資額は、2010年以降は毎年前年比プラスを続けています。これにつれてソフトウェア業界のM&Aは増加傾向にあり、2009年に223件だったM&A件数は2013年頃から増え続け、2018年には1,070件に達しています。
次に高度な技術への対応が求められていることが挙げられます。IT化が進むことで、サイバーセキュリティの強化など、技術的な課題は増えるばかりです。ところがこれに対応する技術者は慢性的に不足しているといわれています。専門的、先進的なノウハウや技術を持った人材を確保し、企業としてのソフトウェア開発能力の向上を図るために、M&Aによる企業買収が進んでいくと考えられます。
参入障壁が低く比較的小規模でも起業できるソフトウェア業界の傾向として、中小企業が多く、下請け、孫請けによる多重下請け構造があります。この最下層の企業は利益率が上がらず、なかなか事業拡大ができません。守秘義務が厳しい業界でもあり、新規受注を声高に宣伝しにくく、信用の拡大が困難という事情もあります。こうした企業が同業種と資本や業務での連携を図ったり、大手企業の傘下に入ることで安定性を求めたりするM&Aも増えているのです。

ソフトウェア企業をM&Aするメリットはどんなことが考えられるでしょうか。
売り手としては、まず大手の傘下に入ることで、安定してより大規模の事業にあたれることでしょう。下層の下請けに甘んじることなく利益率の向上も望めます。また、売却や譲渡に伴う利益を得られることも魅力です。中小企業では経営者が個人的に負債を抱え込んでいる例も見受けられ、こうした負担の解消にも繋がります。さらに会社清算を考える場合、事業そのものはきちんと承継できるとともに、従業員の雇用も安定させられます。
買い手としては自社に不足している技術などを、それを扱う人材とまとめて手に入れるチャンスになります。今までアウトソーシングせざるを得なかった業務の内製化や、業務範囲や販路の拡大も期待できます。

企業のM&Aにおいて買収価額を算定するとき、企業価値をどのように算定化するかが重要になります。企業の価値はその資産などだけから測ることはできず、その企業の持つブランドやノウハウなどもポイントになります。
企業価値を測る方法としてDCF法が用いられることがあります。ソフトウェア企業の場合、自社利用ソフトウェアの価値評価にDCF法を用いることがあります。また、類似企業比較方式も採用されることがあります。これはM&Aの対象となっている企業と同種で、上場されている企業の価格を基準として算定するものです。ソフトウェア企業では、ユーザー数などを基準に企業価値が算定され、広く普及しているソフトウェアを開発していれば企業価値は高めに算定されることになります。
またそのようなソフトウェアの開発に携わった技術者の存在や、製品のプロデューサーが合わせて獲得される場合など、M&Aの相場価格が高くなることもあります。
市場の拡大が見込まれているソフトウェア業界におけるM&Aの場合、他業界よりも高めの相場が設定されるケースが見受けられます。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

ソフトウェア企業を買収するのは、多くは対象企業の持つ技術力を手に入れることでしょう。事業譲渡の形でM&Aを行う場合、特許権の移転を確実に進めることが重要です。この点を見誤ると、最悪その特許を用いた事業が行えなくなってしまいます。
また、買収を行うにあたっての明確な戦略目標の設定や、慎重なデューデリジェンスを行い、技術面でのリスクや顧客契約の継続性に注意を払うことが成功のカギとなります。
こうした点で、M&Aのノウハウを多く蓄積しているM&A仲介会社を利用することも、リスク回避の良い手段といえます。
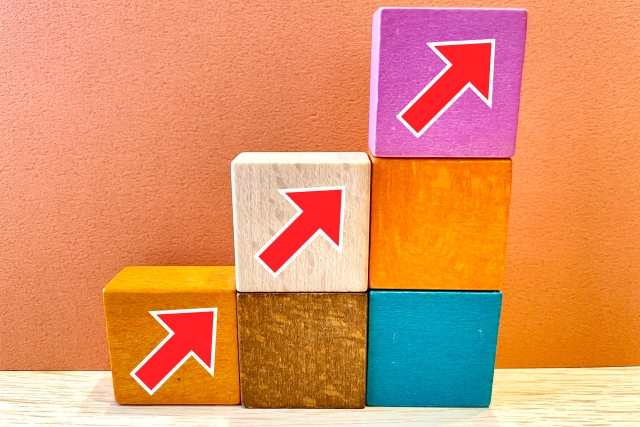
ソフトウェア企業を売却する場合、最も重要なのは企業価値を高める技術力の移転がスムーズに行えるよう図ることです。具体的には、プログラム開発者など重要な人的リソースが仕事を続ける意志があるか確認することや従業員の能力を証明するスキルシートの準備などが必要です。
次に徹底することは労務管理です。社会保険の未加入や給与の未払いなどがあれば売却は困難です。そして、これらの情報が円滑にやり取りできるような買い手企業とのコミュニケーションの確保も大切です。必要に応じて実績豊富なM&A仲介会社などに依頼することも有効です。

ソフトウェア企業をM&Aする際の注意点
ソフトウェア企業のM&Aならではの注意点として、最も大きいのは求める技術やノウハウを手に入れられるかどうかです。
そのためには売り手企業のエンジニアの力量を確実に把握しておく必要があります。
また、そのエンジニアたちを確実に獲得するためにモチベーションの低下を避けなければなりませんし、M&Aの情報告知のタイミングを誤るとM&Aそのものの妨害に及ぶ可能性もあります。
また早期に現金化を求めることが多いこの業界のM&Aでは事業売却が一般的であり、そうなると他社に出し抜かれる危険から、クロージングまでのスピードも大きなポイントになります。

ソフトウェア企業のM&Aはおおむね次のように進みます。
まず戦略の立案です。必要に応じM&A仲介会社に依頼し、目的やスケジュールを明らかにします。
次にソフトウェア企業としての強みなどを分析して企業価値をとらえ、それに基づいてM&Aの相手を選定します。
先方の意向が確認できればトップ会談などをセッティングし、条件交渉などを進めて基本合意書の作成に進みます。ここでM&Aのスキームや譲渡予定価額、スケジュールなどが詰められます。
続いてデューデリジェンスが行われます。ソフトウェア企業の買収にあたっては、特にその技術力などの企業価値の評価が重視されますが、売り手側に法務や税務上のリスクがないかも慎重に調査されます。
問題がなければ最終契約書の締結となります。この契約の内容に従って実際の引き渡しや代表者変更などのクロージングを行い、M&Aが完了します。

M&Aを進めるにあたっては、会社運営などに関する専門的な知識も必要ですが、相手先企業などを広く求めてより有利な取引相手を見つけ出すことが重要になります。
ウィルゲートM&Aでは、15,100社を超える経営者ネットワークを活用し、ベストマッチングを提案します。Web・IT領域を中心に、幅広い業種のM&Aに対応しているのがウィルゲートM&Aの強みです。M&A成立までのサポートが手厚く、条件交渉の際にもアドバイスを受けられます。
一般的にM&Aの成約までは6ヶ月〜1年ほどの期間を要しますが、ウィルゲートでは平均で4ヶ月、最短1.5ヶ月での成約実績、40億円以上での成約実績もあります。完全成功報酬型で着手金無料なので、お気軽にご相談ください。
無料相談・お問い合わせはこちらから ※ご相談・着手金無料
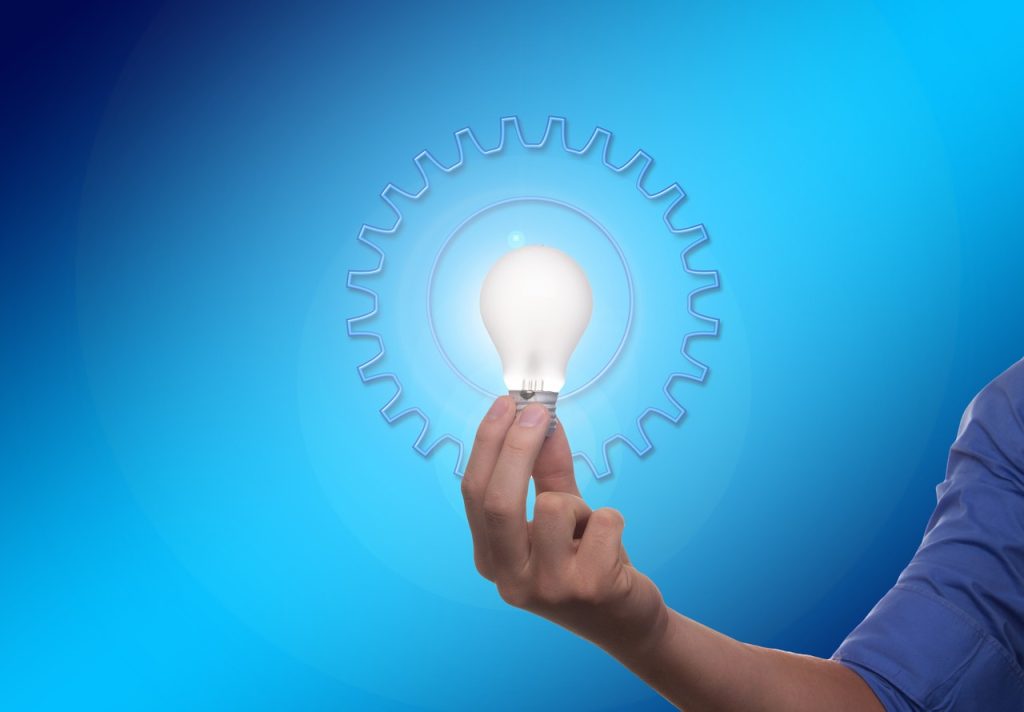
ソフトウェア企業のM&Aは帳簿上などには現れにくい、技術力やノウハウ、人材リソースなどの企業価値を見定めることが重要になります。
また、実際にM&Aを進めることでどのようなメリットがあるかもしっかり見通さなければなりません。自社の企業価値をどう測ればいいか、事業拡大にあたってどんなM&Aが有効か、まず専門家に相談してみたいという方は、ウィルゲートM&Aの無料相談の利用をご検討ください。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください