
M&Aの日本での実施件数は、2019年には4,000件を超えています。成功事例や失敗事例を確認することで、成功者・失敗者に共通するポイントがわかります。この記事では中小企業M&Aのメリットや流れ、注意点などを事例を交えて解説します。

中小企業M&Aは現代で増加傾向にあり、国としてもガイドラインを2020年に作成してM&Aに対して抵抗感をなくすための働きをしています。
2023年に全国で休廃業・解散した企業は5万件を超えており、前年比で約5.8%増加しています。休業や廃業した企業の代表者の年齢は60代が8割を超えていて、事業承継が困難であることが一因となっています。
M&Aは、そのような事態から企業を救うために、現在大手企業のみならず中小企業でも広く行われています。
中小企業は、中小企業基本法により定められている企業のことで、その規模の企業のM&Aが「中小企業M&A」です。まずは中小企業M&Aの概要を把握しましょう。
中小企業M&Aは、中小企業基本法に定められる規模の中小企業をM&Aすることです。中小企業とは、中小企業基本法により以下のように定められています。
中小企業のM&Aは年々拡大傾向にあり、2022年の日本国内のM&A件数は4,304件で過去最高を記録しました。特に中小企業のM&A件数は増加傾向にあり、2021年には3,730件に達しています。
ただし、M&Aを行い、外部の人間が自社の経営に関わることに抵抗感を示す企業が多いのが現状です。この現状に対し、2020年には「中小M&Aガイドライン」が経済産業省・中小企業庁より策定されました。
このガイドラインでは、以下のような内容が記載されています。
国としても、経済活動を活発化させる目的でM&Aの支援をしています。

中小企業がM&Aをする目的はさまざまですが、大きくは「後継者問題の解消」と「事業規模の拡大」、そして「資金調達」に分かれます。
中小企業で抱えている悩みの多くは後継者問題です。超高齢化を迎えている日本で、事業承継がスムーズにいかなく、倒産や廃業している会社があります。倒産や廃業してしまうと、経営者だけでなく働いている従業員や支えてくれた関連企業に影響が出ます。
また、競争が激しい業界の企業であれば、自社の事業規模やシェア拡大が難しい、次の事業への資金調達がうまくいかないなどの悩みがあります。これらの問題を解決する目的で、中小企業M&Aは行われています。
2025年に向けて、日本では経営者の高齢化と後継者不足がさらに深刻化すると予測されており、中小企業M&Aの需要は今後も増加すると考えられています。
中小企業のM&Aの目的の一つに、後継者不足の解消があります。超高齢化社会を迎えている日本で、多くの中小企業の経営者が高齢となり、後継者不足に悩んでいます。仮に後継者となる人物がいても、株式の承継や各種手続き、税負担が大きいなどの理由で事業継承を断念せざるをえない場合があります。
後継者不足で会社が廃業や倒産をしてしまうと、従業員は職を失ってしまいます。そのため、中小企業は後継者を見つけることが、死活問題になっているのが現状です。
M&Aを行うことで、会社を存続させると同時に従業員の働き口も確保でき、売却金が手元に残るなどのメリットがあります。中小企業経営者にとって、会社事業の存続を指せるための手段としてM&Aに注目が集まっているのです。
売り手ではなく買い手側が事業規模の拡大を狙いM&Aをする場合もあります。買い手として、事業拡大のM&Aをするメリットには以下の点があります。
上記以外でも、ライバル企業を買収し、間接的に市場における自社のシェアを広げる目的で使われたりします。自社だけでは成し遂げられないことでも、他社の協力を得て事業規模の拡大が図れます。
自社に足りない売り手企業の技術や営業力、ブランド力などを活用し、買い手企業の事業拡大が図れるのもM&Aの魅力です。
赤字の事業を抱えている会社でも、資金調達さえうまくいけば業績を立て直せる場合があります。
赤字となっている事業でも、他社にとっては魅力的な事業であることは決して珍しいことではありません。その場合、買い手を見つけて売却できると売却金が手元に残り、ほかの事業にお金を充てられます。
このように、売り手企業側が資金調達の目的でM&Aをする企業も存在します。
M&Aを進める際の買い手側の注意点についても留意する必要があります。
M&Aを成功させるためには、まずその目的を明確に定義することが重要です。買い手側は、何を目的としてM&Aを行うのかを具体的に考える必要があります。
例えば、事業の拡大や新技術の獲得、または市場シェアの獲得など、目指す成果を明確にすることで、適切なターゲット企業の選定や交渉戦略に繋がります。目的が不明瞭なまま進めると、思わぬトラブルや目標未達成を招く可能性が高まります。
M&Aにおいて、譲渡企業を慎重に選定することは非常に重要です。買収先の企業が自社の戦略や文化にフィットするかどうかを見極めることは、成功するM&Aの鍵となります。仲介業者の支援を受けながら、財務状況や市場の位置付け、成長性などをしっかりと分析し、最適な選択をすることが成功への第一歩です。
M&Aを成功させるためには、引き継ぐ従業員の条件を明確に整理することが重要です。買い手側は、どの従業員が株式譲渡後に自社に貢献できるかを考慮し、必要な人材を特定する必要があります。
これにより、企業文化の維持や業務の円滑な引き継ぎが実現でき、M&A後の統合プロセスをスムーズに進めることができます。
M&Aプロセスにおいて、デューデリジェンス(買収監査)を十分に行うことは極めて重要です。これは、譲渡対象企業の財務状況や経営リスクを徹底的に分析するプロセスであり、買収後のトラブルを未然に防ぐための鍵となります。
買い手は、透明な情報を収集し、正確な評価を行うことで、適切な判断ができるようになります。デューデリジェンスを怠ると、隠れた負債や法的問題を見逃す可能性があるため、注意が必要です。
M&Aにおいて、オーナーの株式所有割合や人間性は、買い手が譲渡企業を選定する上で非常に重要な要素です。オーナーが持つ株式の比率は、企業の経営権や意思決定に大きく影響します。
また、オーナーの人間性や経営スタイルは、企業文化や従業員の士気にも関わるため、継続的な成功に繋がる可能性が高まります。したがって、買収に際しては、オーナーの人間性をしっかりと見極めることが必要です。
M&Aを進める際、売り手側にも注意点があります。これらをしっかりと把握し、必要なリスク管理を行うことで、円滑な取引が実現できます。
売り手がM&Aを進める際には、適正な企業価値評価(バリュエーション)を持つことが不可欠です。企業価値を正確に把握することで、適切な価格交渉が行えます。
特に契約書においては、評価基準を明記することが重要であり、正当な評価を受けるための基盤となります。これにより、双方にとって公平な取引が実現しやすくなります。
売却を進める際、秘密保持と従業員・取引先への影響管理は非常に重要です。特に、買い手との交渉過程では、企業の内部情報が漏洩するリスクがあります。このため、情報が外部に漏れないようにする措置を講じることが必要です。
また、従業員や取引先への適切なコミュニケーションを行うことで、不安を軽減し、関係性を維持することが求められます。これにより、円滑な取引を実現できるとともに、企業の信頼性を保つことにも繋がります。
M&Aを進める際には、価格条件やタイミングが重要な要素です。特に、売り手が期待する価格と買い手が提示する価格が合致しない場合、交渉が難航することがあります。
また、タイミングが適切でないと、必要な取引が成立しないリスクもありますので、両者は事前に状況を十分に理解し合うことが求められます。
M&Aにおいて、契約条件の確認は買い手にとって非常に重要なステップです。特に、表明保証や競業避止義務といった条件は、取引のリスクを軽減する役割を果たします。これらの条項が明確に定義されていることで、買い手は将来的なトラブルを回避し、安心して事業譲渡を受けることが可能となります。
そのため、契約内容を詳細に確認し、必要ならば専門家の助言を受けることが推奨されます。
表明保証は主に売り手側が行うものであり、買い手のリスク軽減に役立ちます。競業避止義務は通常、売り手側に課される義務です。
買い手の信用力とシナジーを確認することは、M&Aにおいて成功を収めるための重要な要素です。買い手の財務状況や過去の取引実績を評価することで、取引の安全性や安定性を確保します。
また、シナジーの可能性についても検討し、買い手と売り手がどのように相互に利益をもたらせるのかを理解することが求められます。これにより、M&A後の統合プロセスがスムーズに進むことが期待されます。
M&Aにおいては、税務や財務のリスクを把握することが不可欠です。特に、譲渡対象企業の過去の税務申告や財務状態を詳細に調査することで、隠れた負債や将来的な財務問題を予見し、適切なリスク管理を行うことができます。
これにより、取引の安全性を高め、買収後の混乱を避けることが可能になります。

中小企業がM&Aを活用するメリットは、買い手側と売り手側双方にあります。
M&Aを通じて、買い手企業は生産プロセスを統合し、効率化を図ることができます。これにより、無駄なコストを削減し、利益率を向上させることが可能です。
異業種や同業種の企業とのM&Aにより、製品ラインの拡充やサービスの向上を実現できます。これにより、競争相手に対する優位性を確保し、市場での地位を強化することが期待されます。
新たな市場や技術の開発に時間を費やすのではなく、即座に既存の企業のリソースやノウハウを活用できるため、時間の節約につながります。これにより、迅速な意思決定と行動が可能になります。
M&Aを行うことで、市場の変化に迅速に適応できます。特に、急激に変化する市場状況において、柔軟な対応力を持つことは企業の生存に不可欠です。
複数の企業が統合することにより、生まれるシナジー効果は大きなメリットとなります。例えば、技術の共有や顧客基盤の統合により、販売促進やコスト削減を実現し、全体としてのパフォーマンスを向上させることができます。
M&Aを利用することで、規制のある市場や外国市場に対するバリアを突破することが可能です。現地の企業との統合により、必要な法的要件や市場理解を補完し、スムーズな参入を実現できます。
売り手側がM&Aを選択することで、後継者不足の問題を解消し、事業を存続させる道を選ぶことが可能です。
M&Aにより得られる資本とリソースによって、企業の繁栄が期待でき、組織全体の士気や安定性も向上します。
売却後も従業員の雇用を維持することで、企業文化が引き継がれ、業績の安定化にも寄与します。ただし、必ずしも全ての場合に当てはまるわけではないことに注意が必要です。
売り手企業は、M&Aに集中することで、主力事業に注力できるようになり、戦略的方向性を明確にすることが可能です。これは、事業の一部を売却する場合に当てはまるメリットです。
経営者にとっても、最適なタイミングでM&Aを行うことで、利益を最大化し、長期的なビジョンを実現することができます。売り手・買い手それぞれM&Aをする目的があり、双方にとってメリットが期待できるからこそ、数多くの企業がM&Aを行っています。

中小企業M&Aの手法はさまざまで、それぞれメリット・デメリットが存在します。中小企業M&Aには、以下の手法があります。
それぞれのメリット・デメリットを把握し、M&Aを考えている方は、自社にとってどの方法が最適か確認しましょう。M&Aは専門的な知識が必要なので、自社にM&Aに対し専門の知識がある方がいないときはM&Aに詳しい専門家に相談し、最適な手法でM&Aを進めていくのがおすすめです。
株式譲渡は、売り手企業の発行済みの株式を買い手企業が買い取り、経営権を取得することです。数ある中小企業M&Aの方法の中で、一番よく使われている方法です。株式譲渡のメリット・デメリットを把握しましょう。
株式譲渡とは、売り手となる企業が買い手企業に株主を譲渡し、経営を承認させることです。株式譲渡は、株式譲渡契約書を締結後、支払い完了したら株式名簿の書き換えを行うシンプルな方法で、中小企業M&Aで最もよく使われています。
株式譲渡には、「市場買付」「相対取引」「購買買付」の3つの方法が存在します。
市場買付は、証券取引場などで上場企業の株式を購入する方法です。
相対取引は、株式を直接大株主から購入する方法です。
購買買付は、株式買付の募集を不特定多数に行い、株式を市場外で買い集める方法です。
中小企業のM&Aの場合、事業継承目的で行われるケースが多くあります。
株式譲渡のスキームを選択することで、売り手や株主側の利益が最大化できます。
節税の面でも、株式譲渡の対価は分離課税により8割程度売り手の手元に残り、所得に合算され累進課税の対象とならないことがメリットです。
また、買い手側からみても株式を100%保有できれば、M&A成立後に反対株主や少数株主を抱え込む必要がないため、買収後のトラブルを防げます。
株式譲渡のデメリットは、対象会社の帳簿外の株や負債に関する問題を継承してしまうことです。
金銭で見積もり可能な場合はM&Aの対価から差し引かれますが、金銭に換算できない問題の場合、100%株式譲渡以外のスキームを選ばないといけなくなります。
事業譲渡と会社分割は、法的には異なるスキームですが、中小企業M&Aにおいて、100%株式譲渡の次の候補として選ばれています。中小企業M&Aを検討している方は、事業譲渡と会社分割のスキームを把握し、M&Aの方法の選択の幅を持つのがよいでしょう。
事業譲渡とは、譲渡会社の事業の一部またはすべてを他社に譲渡するスキームで、特定承継とも呼ばれます。事業譲渡の場合、会社分割のように登記手続きや債権者手続きに1カ月以上要するわけではなく、手続きが楽です。そのため、移転する契約が少なかったり、従業員の人数が少なかったりする場合、よく使われるスキームです。
事業譲渡のメリットとして、薄外債務を引き継ぐリスクが少ないことや、買い手企業が必要な資産や負債のみを選べる点があげられます。
また、デメリットとしては、個別の資産、取引ごとに譲渡の手続を行わなければならないため手続が煩雑であること、取引先との契約等がうまく引き継げないリスクがあること、免許、許認可等の取り直しが必要であること、譲渡益に対して法人税が課されることなどがあげられます。
特に譲渡する資産や負債の詳細なリストアップを行わないと、後々のトラブルに繋がることも考えられます。
これらのメリット・デメリットを理解し、ほかのM&Aの手法と比較し、事業譲渡をするか検討するとよいでしょう。
会社分割とは、事業の権利義務を一部または全部他者に承認することです。
会社分割のスキームには「吸収分割」と「新設分割」があります。
吸収分割は、既存の会社に権利義務を承継させることです。
この手法は、効率的な資源の再配置や、事業の特化を図る際に非常に有効です。
新設分割は、新たに設立する会社に権利義務を承継させることです。
この手法は、特定の事業や資産を他の事業から分離し、専門的な運営を行うことが可能になります。
さらに、「分割型分割」と「分社型分割」にスキームが分かれます。
分割型分割は、分割会社の株主が分割の対価を受け取ります。
この手法は、企業が特定の事業部門を独立させることを考えている場合に使用され、事業の専門性を高めることができます。
分社型分割は、分割会社自身が分割の対価を受け取ります。分社型分割が選ばれるのは、事業譲渡を行うと契約数が多くなり手間がかかる場合です。
この手法では、既存の会社が一部の事業を新設の法人または既存の法人に移転する形をとります。
会社分割は、企業が特定の事業や資産を新設または既存の法人に移転する方法です。この手法にはいくつかのメリットとデメリットが存在します。
会社分割のメリットは、以下の点があげられます。
対して、会社分割のデメリットは以下の点があげられます。
会社分割のメリット・デメリットを把握し、他のM&Aの手法と比較し会社分割の方が良いか確認し、M&Aを検討している方は進めていきましょう。
株式交換は、100%子会社の完全子会社となる企業の株式と完全親会社の株式を交換するスキームです。
株式移転は、親会社と子会社の関係を作る方法ですが、親会社になるのが新設会社である点が、株式交換と違います。
株式交換の仕組みや株式移転との違いを把握しましょう。
株式交換を行う目的は、対象の企業の子会社化です。最終的に対象企業の株を買い手がすべて所有する点では、100%株式譲渡と同じです。
ただし、株式交換は組織再編を行うので、全体のフローが長期間で煩雑になる恐れがあります。
株式移転とは、完全子会社の株式と新たに設立する会社の株式を交換して、持ち株会社を設立するスキームです。
株式交換や株式移転には、それぞれ独自のメリットとデメリットがあります。
株式交換・株式移転のメリットは、以下の点があげられます。
株式交換・株式移転のデメリットは、以下の点があげられます。
特に、既存株主が不満を抱くことがあるため、事前のコミュニケーションが欠かせません。
また、法的および税務上の問題が発生するリスクもあります。株式交換や株式移転を検討している方は、株式交換・株式移転のメリット・デメリットを把握し、専門家に相談をしましょう。

中小企業M&Aの手続きの流れを確認しましょう。
M&Aを行う上で重要なのは、目的を明確にすることです。
自社の課題を洗い出し、今後の事業計画などを踏まえたうえで、自社の問題を解決する方法は、M&A以外にもある中で、本当にM&Aを行う意味があるのか、M&Aでなければいけない根拠を明確にし、社内で議論しましょう。
目的が明確になったら、どの企業に売却するのか探し、条件があう企業を見つけたら交渉に入ります。交渉を円滑に進めるためには、M&Aに詳しい専門家や仲介サービス業者のサポートを受けるのがおすすめです。
多額の金額が動くM&Aでは、トラブルが起こる恐れがあります。専門家を入れることでトラブルを回避し、スムーズに契約が進むでしょう。
M&Aで売却先の企業を選定する前に、M&Aを行う目的を明確化するのが重要です。
自社の課題や今後の事業計画について具体的に策定し、M&Aを行う必要があるのか社内で議論しましょう。
M&Aを行わなくても、自社の課題が解決する方法は他にもある中で、なぜM&Aでないといけないか、根拠を明確にすることで、この後の交渉や手続きがスムーズになります。
M&Aの目的を明確にした後、M&Aのスキームを決めますが、自社にM&Aのノウハウがない場合、外部の専門家に相談をしM&A成立後までアドバイスを求めましょう。
M&A仲介会社を通す場合、仲介会社から提供されるノンネーム資料を元に買い手の企業を探します。ノンネーム資料に記載されているのは、業種や事業規模、エリアや買収する理由などで、具体的な企業名は不明です。
資料の情報を元に売却する希望を絞り、秘密保持契約を結んだうえでほかの情報開示を行います。このとき、買い手企業は売り手企業の「登記簿謄本」や「定款」などを取得して企業情報の確認をするので、売り手企業側は事前に準備しておくとよいでしょう。
本格的な契約を行う前に、売り手企業と買い手企業の双方のトップが面談を行います。トップ面談は、売り手と買い手の経営者同士が、お互いの人間性や経営理念などを確認しあう重要なプロセスです。
お互い、大切な従業員や今まで関係を築いてきた企業があります。それらを巻き込むのがM&Aなので、安心して関係を築ける会社同士のM&Aでないといけませんよね。
お互いの経営者としての人間性や経営理念が似通っていれば、M&A後もスムーズに経営ができます。契約面の交渉を行う前に、M&Aを行う目的の確認や双方の企業に関する情報交換を行い、齟齬が生じなければ交渉に入ります。
M&Aで基本合意とは、買収監査の実施前に、売り手と買い手企業の当事者同士で契約内容に合意している状態を指します。基本合意において、以下の内容を定めます。
基本合意のうえ、買収監査を実施します。買収監査とは、基本合意締結後に買い手企業が売り手企業の実態を把握するために行う調査です。買収監査は、外部のM&A専門家が派遣され、売り手企業の設立時まで遡り調査します。買収監査終了後、最終合意に向けて、今後のスケジュールや役員の処遇について決定します。
最終的な売却条件が決定後、お互いに契約内容に相違がなければ最終契約書を締結します。
決済までに売り手側に要求される事項として、「制約事項」と「クロージング条件」があります。
制約事項とは、譲渡日までに行う必要がある事柄です。
クロージング条件とは、決済に関する取り決めが定められます。
クロージング手続きとして、株券や会社代表印の引き渡し、買い手企業から売り手企業に対して譲渡金支払いや、売り手企業経営者の私的資産買い取りなどが行われます。
買収後の経営統合の作業を「PMI」と呼び、PMIはM&Aのプロセスで重要な要素です。
PMIは通常クロージング前から始めることが多く、統合方針の決定から始まり、ランディングプランの策定を行います。
その後、100日プランの策定を行い、統合実施効果検証を行います。

中小企業のM&Aを成功させるためのポイントを把握しましょう。中小企業M&Aを行う上で重要なのが、まずがM&Aを行う目的を明確にすることです。
M&A以外で良い方法がないかを考え、M&Aでなければいけない理由が見つかると、その後の買収企業を選んだり交渉したりするのもスムーズに進みます。M&Aは多くの方を巻き込み行うので、自社だけでなく相手企業に関わる方への配慮を持ち、事前にM&Aに強い人材を社内だけでなく社外からも招くのがおすすめです。
また、M&Aは最初の時点では株主の情報が不明な部分があるので、交渉を進めるうえで情報開示を求め、相手企業の情報を明確にしましょう。交渉を進める前に、事前に買収価格の上限価格と下限価格を決めたうえで交渉に入るのも、その後の交渉を有利に進めるポイントです。
M&Aを行う企業の目的は、事業継承や事業拡大などさまざまです。M&Aを成功させるにあたり、M&Aを行う目的を明確にすることが重要です。
たとえば、事業継承においては、親族や社内役員へ承継させるなど、方法はM&A以外にもあります。
M&Aを行う目的が不明確だと、取引相手の企業を選ぶ基準も明確化できず、交渉がうまくいきません。最初からM&Aを前提とせず、目的を明確にしたうえで他の方法と比較し、しっかりと検討しましょう。
売り手企業の社員や取引先などの関係者に与える影響を考慮することも大切です、買収を行うことで対象企業の顧客やと取引先、従業員に大きな影響を与えます。
M&Aは身売り行為というイメージがある方が多いので、PMI後も滞りなく経営を行うために、今まで対象企業に関わった方への説明責任を果たし、信頼関係を築きましょう。
中小企業は株主名簿が存在しなかったり、株主の所在がはっきりしなかったりする場合があります。中小企業M&Aで株式譲渡を選択する場合、買い手企業は株式に対し対価を支払います。
そのため、株主を把握しておかないと、まったく関係ない第三者に多額の支払いをすることになる恐れがあります。
また、株式名簿が作成されていても、そこに記載されている株式譲渡が株主の承認を得ているか不明な場合があります。買収監査の際に資料と照らし合わせ、矛盾がないか確認する必要があります。
買い手企業がM&Aを行うときには、社内でチームを形成して進めていきます。
M&Aは秘匿性の高い案件で、専門的な知識が要求されます。社内の人間だけでM&Aを進めるのではなく、社外でM&Aに詳しい専門家を招くことがおすすめです。
M&Aには多額の費用が発生し、税金も課せられるので、自社だけで完結せず社外の方の意見も聞き入れて進めていきましょう。
M&Aにおける重要なポイントとして、買取価格があります。M&Aにおいて、買い手企業は買収企業に対し価値算定をしますが、その際に買収価格の上限と下減を設定するのがおすすめです。
この場合、上限価格は買い手企業の留保価格とし、対象企業の時価にPMI後に得られる自社の収益を足した値段にします。下限価格は、売り手企業に対し最初に掲示する価格で、対象企業の現時点での清算価値の値段にします。
M&Aの交渉において、最初に下限価格を掲示し、それが売り手企業の想定の価格に近ければ、その後の交渉もスムーズに有利に進められます。金額を掲示するときに、価格を算定した根拠をプラスで掲示すると説得力が増します。

中小企業M&Aは近年増加の一途をたどっています。中小企業M&Aの成功事例も数多くあり、中小企業M&A仲介会社のホームページに具体的な実例が紹介されていることもあります。
成功事例を確認すると、M&Aを成功させるためのポイントが確認できます。成功者に通じているのは、M&Aをする目的を明確にし、経営理念と想いが相手企業とマッチングしたうえで契約を締結していることです。
成功事例を確認し、M&Aを成功させる秘訣を確認しましょう。
千葉県の金属加工メーカーA社が今後の事業拡大のためにM&Aを検討し、M&Aプラットフォームに登録して、同業の金属加工メーカーB社に巡り合いました。
B社の代表は引退を考えていて、その中で代表者の「雇用と技術を守りたい」という熱い思いからM&Aを検討していました。A社は技術力の育成が課題でM&Aを検討していました。
双方の思いがM&Aを成立させてシナジーを生み出し、現在は収益も増加しています。両社のM&Aをする目的が明確であったため、契約後も業績があがった事例です。
IT系コンテンツを配信するオウンドメディアを他社に売却し、その資金をもとにホームページ制作やWeb集客コンサルティングなどの新規事業に着手し、成功した事例です。
売り手企業はもともと経営状態は順調でしたが新しい事業に挑戦したいと考え、事業資金を確保するためM&Aプラットフォームに登録しました。
その後、十分な資金と希望する運営体制が整っている会社と出会い、M&Aが成立しました。銀行融資などを受けず、ノーリスクで新規事業を立ち上げ、今では順調に新規事業が進んでいます。
東京都内で美容室を3店舗経営する売り手企業が、東証一部上場企業へM&Aを成功させた事例があります。
家庭の事情で事業承継をすることになり、美容室業界の働き方に改善が必要と考えていた売り手企業の代表が、業界の常識にこだわらず、事業を成長させられるプロの経営者を求め、M&Aプラットフォームに登録しました。
買い手企業は東証一部上場の大企業で、買い手企業以外にも上場企業数社からM&Aの話がありました。売り手企業の経営者の思いが、東証一部上場企業の代表を動かし、M&Aを成立させた事例です。
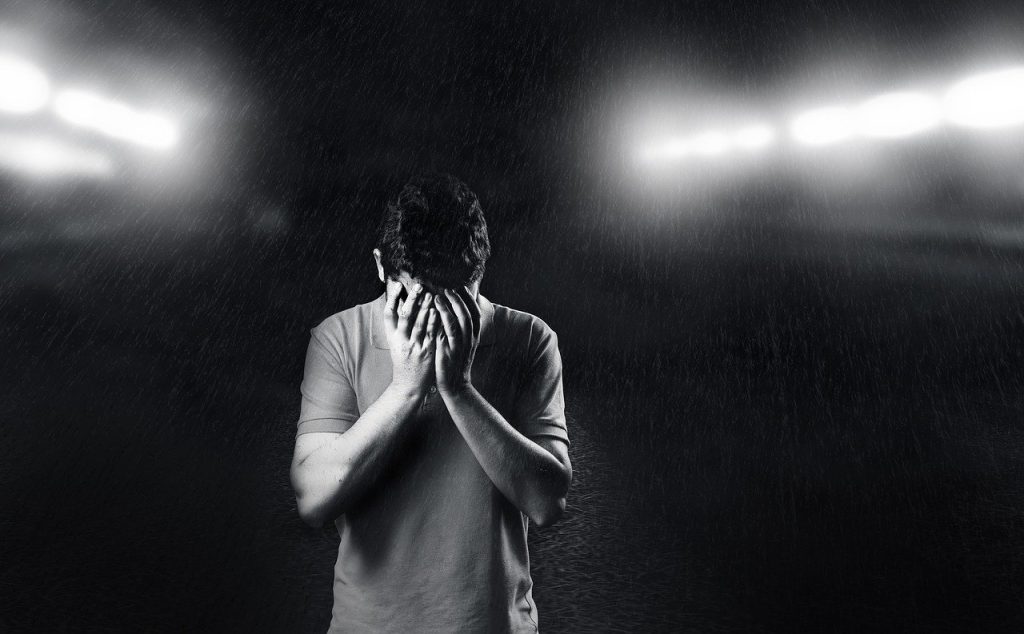
中小企業M&Aにおいて、交渉がうまくいかなかったり、最終段階で交渉打ち切りになったりした事例があります。
M&Aがうまくいかなかった事例は数多くあり、失敗事例には共通事項があります。失敗事例を確認することで、M&Aを進めるうえで気を付けないといけないポイントがわかります。
M&Aを検討している方は失敗事例を確認し、同じ過ちをおかさないようにしましょう。
売り手企業のA社が、代表の高齢化による後継者不足を理由にM&Aを検討していました。
A社は、日々の業務に追われ後継者問題について考える余裕がなく、金融機関からの借り入れなどで事業は継続してきましたが、徐々に業績が悪化してきました。資金繰りが悪化する中でA社代表は弁護士に相談し、弁護士は買い手企業を探しました。
しかし、すでにA社の活気は失われていて、M&Aは不成立に終わりました。日々の業務に追われ、M&A着手が遅れたため失敗した事例です。
後継者不足によりM&Aを探していたB社が、M&A専門業者に相談を行いました。
仲介業者が迅速に動いたため、M&A着手から4カ月で買い手企業とのマッチングが実現し、基本契約に合意し最終契約に向けて動いていました。
しかし、B社の代表者が情報漏洩をしていたことが発覚し、その後再三に渡り警告を受ける事態になりました。
最終契約前に従業員が一部取引先や関係者に買い手企業の名前を明かし、M&Aを行うことを公表したところ、情報漏洩に激怒した買い手企業が激怒し、信頼関係を理由に交渉を打ち切りました。
売り手企業が情報漏洩をしたため、M&Aが不成立になった事例です。
A社は地域密着型で運送業を営んでいましたが、代表の高齢化で事業承継問題に直面し、M&Aを決意。すぐに同地域の買い手企業とマッチングが成立しました。
しかし、だんだんと会社を手放すのが惜しくなったA社が、譲渡条件を急に変更しました。買い手企業はA社の不誠実な対応に嫌気がさし、信頼関係が損なわれ交渉を中止しました。
基本合意締結に至った後、売り手企業の不誠実な対応により交渉が決裂した実例です。

中小企業M&Aにおいて、企業をマッチングし契約を進めていくうえで、専門知識を持った仲介会社を利用するのがおすすめです。
M&Aの仲介会社の中には、中小企業のM&Aを専門に取り扱っている企業があります。仲介会社を挟むことで、売り手にとっても買い手にとっても最適な相手探しを行えます。
仲介会社を選ぶ際には、自分で探すだけでなく、地域で開設されているM&Aの相談窓口も利用できます。仲介会社選びも含め、M&Aについて気軽に相談してみましょう。
中小企業向けのM&A仲介会社を選ぶときは、仲介会社の過去の実績や在籍するスタッフのキャリアを確認しましょう。
仲介会社を選ぶときは、自社のM&Aをする目的を果たせる会社を選ぶのが重要です。
M&Aをする目的は事業承継や資金調達、企業規模拡大などさまざまです。仲介会社によって、得意な分野が違います。
仲介会社の公式ホームページで、M&Aの実績や在籍するスタッフのキャリアや保有資格などが掲載されているケースが多くあるので事前に確認し、自社の悩み解決の実績がある仲介会社を選びましょう。
中小企業向けのM&A仲介会社を選ぶときには、地域の機関に相談しながら選んでいくのがよいでしょう。
日本ではM&Aが活発に行われていて、国としてM&Aを支援する動きがあります。
各都道府県で、事業引き継ぎセンターや金融機関、商工団体や士業専門家などに相談できます。各機関で専門とする分野や支援サービス内容が違うので、事前に確認しましょう。
また、M&A仲介サービス(M&Aプラットフォーム)とよばれる、オンライン上で企業のマッチングできるサービスがあります。低コストで利用できるサービスがあるので、M&Aを検討している方はまずは登録だけしてみてもよいでしょう。
事業引継ぎ支援センターとは、中小企業M&Aの支援を目的に2011年(平成23年)に設置された国の機関です。
令和2年時点ですべての47都道府県に設置されていて、M&Aのみでなく従業員承継など事業承継に関する幅広い相談が可能です。事業引継ぎ支援センターは、経済産業省の委託を受け、各都道府県の財団や商工会議所などが運営する事業で、地元の各士業専門家や金融機関OBが常駐しています。
事業引継ぎセンターで可能なM&A支援は以下の通りです。
金融機関でも、貸付を行っている顧客に対しM&A支援を行う場合があります。
金融機関による中小企業M&A支援の場合、M&Aを検討している企業同士のマッチングをしたり、金融機関が持つ顧客の中で候補者を絞ったりすることが可能です。
ただし、都市銀行や地域銀行、信用金庫により、M&Aに対する取り組みが違います。
金融機関で受けられるM&A支援は以下の通りです。
中小企業団体や商工会議所、商工会や中央会商店街振興組合連合会などの商工団体が、地域発展のために中小企業M&Aの支援を行う場合があります。
商工団体は地域に根差している特性があり、中小企業が受けられる公的な支援制度についても熟知していて、中小企業にとって身近な相談窓口です。
商工団体は、税務や法務の祖団よりは経営に関する相談が多く、地域の中小企業の経営状況などを認識しています。
商工団体で受けられるM&A支援は以下の通りです。
弁護士や税理士、公認会計士などの士業専門家から、中小企業M&Aの支援を受けられます。
弁護士は、法律の専門家の立場でM&Aに関する相談にのってくれます。
中小企業M&Aで弁護士から受けられる支援内容の一部は以下の通りです。
税理士は、税務会計に精通しているので、M&Aにおいて経営支援や金融支援の立場からサポートしてもらえます。
税理士が支援できる範囲の一部は以下の通りです。
公認会計士は、会計の専門家の立場から税務に関する情報の整理をして、売り手企業の信頼性の向上においてM&Aのサポートをしています。
公認会計士によりM&Aの支援内容の一部は以下の通りです。
M&A仲介サービス(M&Aプラットフォーム)は、インターネット上で売り手企業と買い手企業のマッチングを支援するサービスです。
サービスごとに利用可能な対象者や利用方法が異なりますが、売り手企業も買い手企業も登録可能で、低コストでかんたんに利用できます。
成果報酬型のサービスも多く、まずは相談だけするのも可能です。
M&Aで多額のコストを投入できない企業にとって、おすすめのサービスです。
M&A仲介会社は、M&Aの仲介業務やファイナンシャルアドバイザー業務に従事する専門家で、M&Aにおいて重要な存在です。
M&A仲介会社には、マッチングから交渉に関するまで幅広い支援が可能です。
ただし、M&A仲介業務自体には法定の資格要件がないため、選ぶときは注意が必要です。
事前にM&A仲介会社のホームページなどを確認し、士業専門家の資格があるスタッフが在籍しているか、今までのM&Aのサポート実績などを確認してからサポートを依頼しましょう。

ウィルゲートM&Aでは、15,100社を超える経営者ネットワークを活用し、ベストマッチングを提案します。Web・IT領域を中心に、幅広い業種のM&Aに対応しているのがウィルゲートM&Aの強みです。M&A成立までのサポートが手厚く、条件交渉の際にもアドバイスを受けられます。
一般的にM&Aの成約までは6ヶ月〜1年ほどの期間を要しますが、ウィルゲートでは平均で4ヶ月、最短1.5ヶ月での成約実績、40億円以上での成約実績もあります。完全成功報酬型で着手金無料なので、お気軽にご相談ください。
無料相談・お問い合わせはこちらから ※ご相談・着手金無料

中小企業M&Aは、現代日本でも実施件数が増加しています。
M&Aをする目的は各社さまざまで、成功している例もあれば失敗している例もあります。これからM&Aを検討している方は、そうした成功例・失敗例から学び、自社でM&Aをするときは必ず成功させましょう。
中小企業M&Aを行うときは、中小企業M&Aの実績が豊富な仲介会社にサポートしてもらうのがおすすめです。
ウィルゲートM&Aでは利用者数が1,400社を超えている実績豊富なM&A仲介会社です。完全成功報酬型で着手金無料なので、M&Aを検討している方はご相談ください。
無料相談・お問い合わせはこちらから ※ご相談・着手金無料
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください